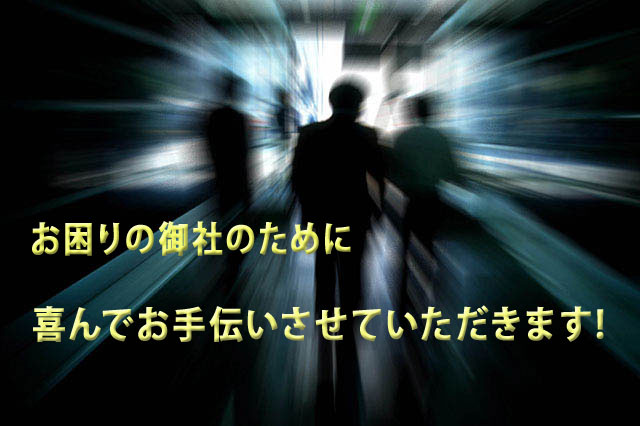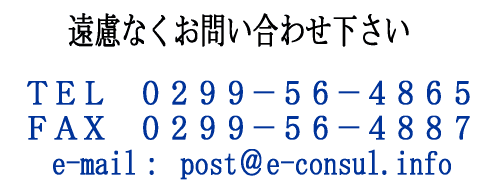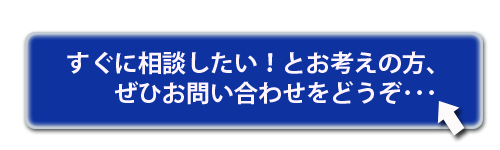作成日:2021年09月28日
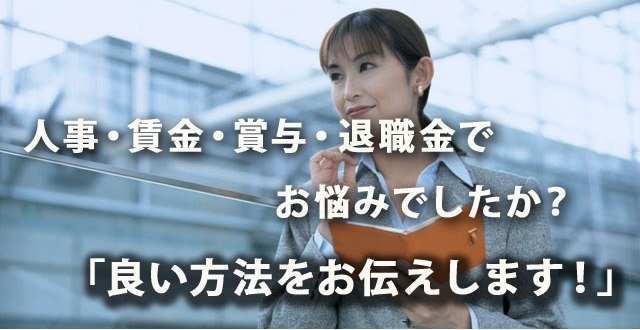
- 評価制度を作りたいけれど、やり方が分からない
- 成果主義・業績連動にしたいけれど、どうしたらいいのか・・・
- 社員のやる気を上げるにはどうすればいいの
- 社員一人ひとりをみて、納得のいく賃金・賞与・退職金の設計がしたい
- 職務要件を自社に合わせて決めたい、そして幹部社員育成がしたい
- 有名コンサル会社からノウハウを買ったけど全く動かせていない・・・
- 社員のレベルアップが鍵なのは分かっているけど教育訓練も出来ていない
社員の成長や戦力化を目指した人事賃金制度構築をサポートします
熟練した社労士事務所なので安心して委託下さい。次のように解決します。
- 人事制度診断と御社に適した人事制度構築の指針を検討します
- 人事評価制度の策定を行います
- 昇格制度の策定を行います
- 賃金制度の策定を行います
- 賞与や退職金に人事政策を反映すべく検討します
- コンサル後は低料金の顧問契約で長期間フォローします
- 助成金を活用して低コストでの制度構築や運用支援が可能です
- 業務標準化や教育体系整備、研修支援もオプションで承ります
人事・賃金・退職金制度構築&サポートでよくある質問
- 人事制度構築のポイントはなんですか?
- 評価項目の選定・決定と、コア業務に連動させて業績アップを目指した評価項目を自社に合わせて構築できるかです。目的を人材の戦力化、業績アップとして、それをずらさずに構築していくことがキーポイントです。
- 制度構築までの期間はどの程度ですか?
- 標準で1年間をみています。全体の整合と評価者訓練などまで含めてのスケジュールになりますが、モデルの工程表などはすぐにご提供できますので、遠慮なくお問合せをしてみてください。
- 一度構築すれば組織問題は解決しますか?
- 最初構築した段階で解決するのは至難の業です。運用しながら継続的改善を図り、完成に近付けていくことが大切です。運用し出すと不具合が見えてきます。動かさないと結局のところ使い勝手が良くなりません。
- 賃金テーブルだけ決めればいいんじゃないですか?
- 賃金テーブルだけを動かして良くなった会社を見たことがありません。人は評価されたように動くと言います。誰しも褒められれば嬉しいですし、叱られれば嫌なものです。組織内での是々非々を明確にして、基準や解釈尺度を統一して、みなで同じ言語・道具を使って高みを目指すことが重要です。よって賃金だけではなく、最初は評価制度構築から入ることがセオリーです。
- 業績連動の良い手立てはありますか?
- 間違いなくあります。とだけお伝えしましょう。詳細はお目にかかってお伝えしたいと存じます。
- うちの幹部連中に評価させるなど想像できません
- そう仰る経営者は結構な数います。その気持ちも良く分かります。しかし、それではいつまでも社長が部下を評価し続けなくてはいけません。社長の仕事は大所・高所から眺め、時代やマーケットを適切に捉え、部下たちに迷わずに方向性を示して引っ張っていくことです。
- 委託することで他にメリットはありますか?
- その質問をお待ちしていました。
当事務所は、「ISOコンサル」、「業務改善」、「教育訓練支援」を得意としている事務所です。従いまして、そうしたノウハウの提供にこそ当事務所の強みがあると考えております。
組織運営されるにあたり、様々な人の悩みがあろうかと思いますが、その時こそ我々にご用命いただければ幸いです。ただしご質問等にお答えできるのは顧問契約をしている企業様に限っています。
構築後もアドバイスがお望みでしたら、顧問契約をご検討願います。
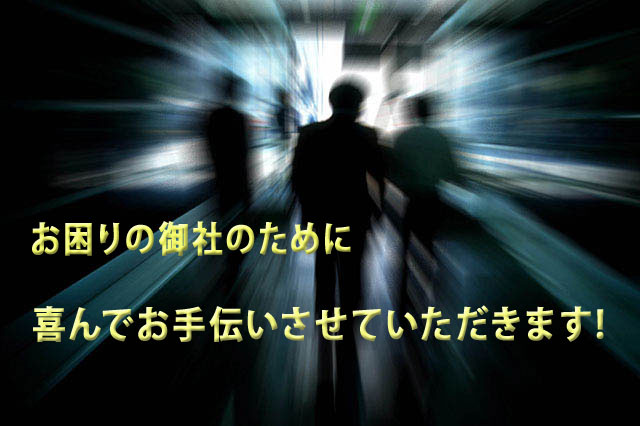
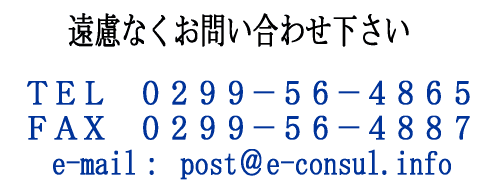
人事制度運用が成功した暁の効果
評価とは、評価制度がある、ないということではありません。
「彼(部下)はこの一年で○○が出来るようになった」とか
「彼(部下)はこの半年間かけたが○○がまだまだできていない」と評価することです。
言葉を変えれば「誉める」こと「叱る」こと。
そんなことはきっとどの会社でもやっていることでしょう。それが社長なら、その誉めちぎられた社員は、昇給したり賞与が増えたりと、処遇までストレートで続いていくでしょう。社長にとっては誉める回数が多い社員は処遇が良くなるのは当然のことです。もし、社長が毎日のように誉めても、昇給もなく、賞与も同じなら、誉められる行動を取らなくなります。賃金でやる気をださせることは出来ませんが、逆に取り扱いを間違えると不満要因になります。
人事制度は人を育てる仕組みだと言えます。人事制度をつくることによって社員が成長しなければならないはずです。企業にとって社員が成長するとは、業績が向上することを意味します。もし、結果として業績が向上しなければ、失敗と考えます。
最大の問題点は、人事制度をつくり評価を実施すると管理者と社長との評価が一致しないことです。よって社内の評価基準や解釈の尺度を一致させ、どこを目指しているのかを強固に共有して、業績アップにつなげていくことが答えです。繰り返しますが、業績が向上しなければ失敗であり、成功していれば業績がアップしているはずです。